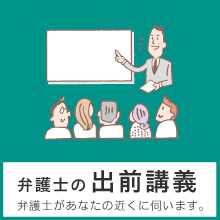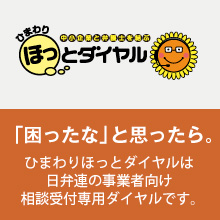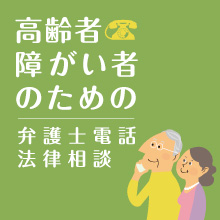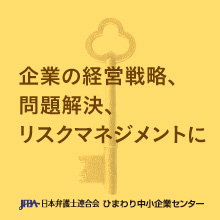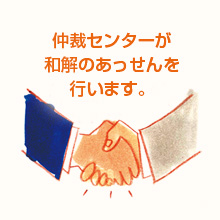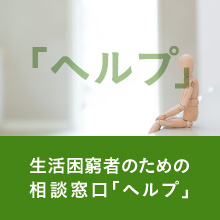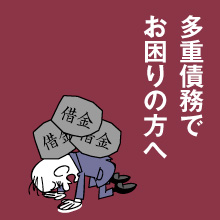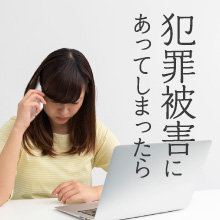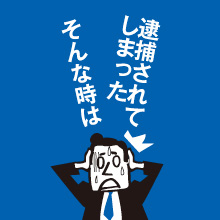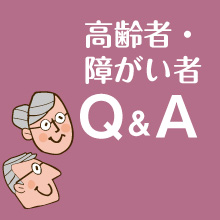会長声明・意見
憲法記念日を迎えるに当たっての会長談話
2025/05/01
1 本年8月15日は、終戦から80年となります。
現在、世界では2022年2月にロシアによるウクライナ侵攻、2023年10月からはイスラエルとパレスチナのハマスの紛争など、世界各地で武力紛争が起きています。
ウクライナやパレスチナのガザ地区では核兵器の使用の危険性が高まり、世界に不安をもたらしています。
我が国は、人類史上初めて、1945年8月6日に広島、同月9日には長崎に原子爆弾が投下されました。原子爆弾の投下による死者は広島で約14万人、長崎で約7万人と言われています。多数の国民の命が奪われました。
戦争は最大の人権侵害です。それゆえ、日本国憲法は、前文で「日本国民は」…「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」しました。
今こそ、日本政府は、日本国憲法が掲げる恒久平和主義、国際協調主義の原理に基づき、国際平和の維持のために最大限の外交努力を尽くすべきです。
2 また、日本のひとり親世帯の相対的貧困率は、44.5%(2022年国民生活基礎調査・厚生労働省)であり、OECD平均の31.1%(OECDFamilyDatabase"Child poverty2023年7月19日閲覧)よりも高くなっております。
憲法は、13条により幸福追求権を、25条により「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を保障しています。しかし、現状は、十分とはいえません。
一人一人が自分の生き方や自己決定できる機会を保障し、誰もが安心し、安定した生活を送れるようにすべきです。
3 現在、再審法改正をめぐる動きが佳境を迎えております。
「袴田事件」や「福井女子中学生殺人事件」などのえん罪事件を通じて、再審法の不備により、えん罪被害者やその家族らの人権が極めて長期にわたり侵害されてきたことが明らかになりました。再審法改正の速やかな実現を求める世論も、かつてないほど高まっています。
「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟(再審法改正議連)」は、本年2月26日、刑事再審に関する刑事訴訟法の一部を改正する法律案骨子たたき台(以下「再審法改正案」といいます。)の取りまとめを行うとともに、今国会(第217回国会)に再審法改正法案を提出し、成立を目指す方針を明らかにしました。この再審法改正案では、①再審請求審における証拠の開示命令、②再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、③再審請求審等における裁判官の除斥及び忌避、④再審請求審における手続規定の整備を内容としています。この動きに対して、法務大臣からは再審制度の見直しを法制審議会に諮問する方針が表明されておりますが、まずは改正の必要性、緊急性が高い上記4項目について、議員立法による再審法改正案を今国会で速やかに成立させるべきと考えます。
4 加えて、今国会では、選択的夫婦別姓制度の導入についても、議論がなされています。
当会では、夫婦同姓を強制している民法750条について、2024年12月4日付け「直ちに民法750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明」を発出しています。
夫婦同姓により、実際には、婚姻した夫婦の約95%において女性が改姓して男性の姓に合わせるという形が取られており、事実上女性が不利益を受けており、人権が侵害されているといえます。
現在「通称使用の拡大」が検討されていますが、それでは改正を強いられた方に生じている様々な不利益はなくならないといえます。一般社団法人日本経済団体連合会も、「通称」使用では解決が困難な課題も少なくなく、女性が活躍する社会においては、「通称」使用に伴う課題が企業にとってもビジネス上のリスクとなり得る事象であるとして、選択的夫婦別姓制度の導入を求めています。
海外では各国が夫婦同姓を強制する制度を廃止しています。国際連合の女性差別撤廃委員会は、2024年10月29日、国連女性差別撤廃条約の実施状況に関する第9回日本政府報告書に対する総括所見の中で、女性が婚姻後も旧姓を保持できるよう夫婦の姓の選択に関する法律を改正することについて、4回目の勧告を行っています。1996(平成8)年に法制審議会が制度導入の民法改正案を答申してから、約30年になろうとしています。法制化を望んでいる国民が全国で多く待機しています。
選択的夫婦別姓制度の導入により、家族の一体性が損なわれるという意見があります。しかしながら、夫婦別姓制を採用している諸外国において、家族の一体感が弱まっているというような報告は聞きません。また、戸籍制度がなくなることもありません。さらに、本年3月27日の政府答弁でも触れられていましたが、子どもに悪影響を与えるものでもありません。
現在、多様性(ダイバーシティ)社会の実現が国の施策ともなっていますが、様々な夫婦や家族の形態を許容することにより、多様で寛容な活力ある社会が生み出されるといえます。
今国会において、選択的夫婦別姓制度が導入されるべきです。
5 最後に、同性婚制度についても、直ちに導入がなされるべきです。
同性間の結婚を認めない民法と戸籍法の規定について憲法違反を問う裁判で、本日までに5つの高等裁判所の判決で、これら規定を「違憲」と判断しています。
当会からも2025月2月27日付け「直ちにすべての人にとっての平等な婚姻制度を実現するための民法等の法改正を求める会長声明」を発出しておりますが、福岡高等裁判所の2024(令和6)年12月13日の判決では、同性カップルを婚姻制度の対象外とする本件諸規定は、憲法24条2項(婚姻の自由)及び憲法14条(法の下の平等)に加え、幸福追求権を定める憲法13条にも反するとの画期的な判断を示しています。
裁判はこれから最高裁判所で審理がなされますが、国においては同性婚導入の検討の着手が未だなされていないといえます。しかし、5つもの高等裁判所による違憲判決により、裁判所は国による立法行為を強く促しているものであり、最高裁判決が出る前に、国は直ちに同性カップルも異性カップルと等しく同じ婚姻制度を利用できるように法改正を行い、同性婚制度を速やかに導入すべきです。
6 私たち山口県弁護士会は、日本国憲法を頂点とする立憲主義の立場から、平和主義を堅持し、国民主義に基づく政治を実現することにより個人の人権を守る立場から、引き続き、憲法の趣旨を踏まえて制定された弁護士法1条が弁護士・弁護士会の使命とする、基本的人権の擁護と社会正義の実現のための活動を積極的に行ってまいります。
2025(令和7)年5月1日
山口県弁護士会 会長 浜崎 大輔
山口県弁護士会 会長 浜崎 大輔