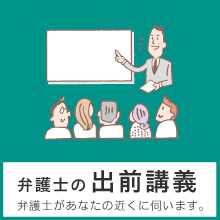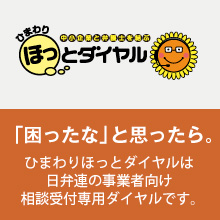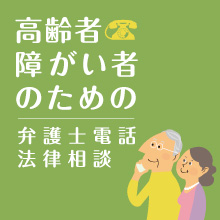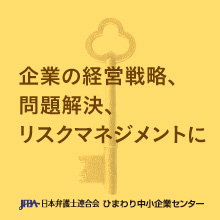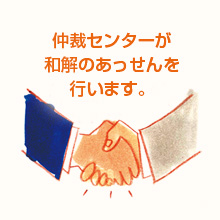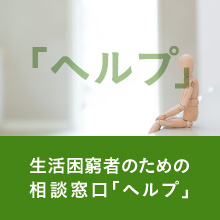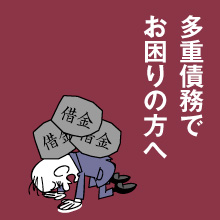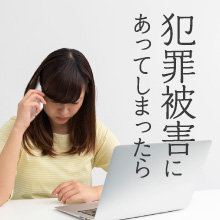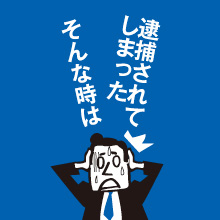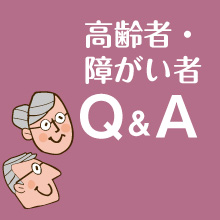会長声明・意見
日本学術会議法案に反対する会長声明
2025年(令和7年)4月30日
山口県弁護士会
会長 浜 崎 大 輔
山口県弁護士会
会長 浜 崎 大 輔
しかし、そもそも学術会議を廃止する立法事実があるとはいえないうえ、本法案は、新法人の政府に対する独立性を失わせ、学問の自由(憲法23条2項)を害する危険の高い法案であって、当会は、この法案に反対する。
すなわち、わが国では、明治憲法下において、滝川事件(刑法学説が自由主義的であるという理由で教授が休職を命じられた事件)や天皇機関説事件(天皇が国家機関であるとする学説が国体に反する異説とされて著書の発禁処分等がされた事件)などのように、学問の自由が直接に国家権力によって侵害された歴史を踏まえて、学問の自由が、思想の自由及び表現の自由と重ねて、現行の憲法に明文で規定された。また、学問、とくに科学は客観的真理を探求するものだから、多数決原理に立脚する民主主義的統制に馴染まない。
だからこそ、学術会議は、学問の自由からくる要請として、国の特別の機関として設立されたものであって、学術会議が、この要請に応えなかったという事実もない。実際、2020年(令和2)年10月1日に菅義偉内閣総理大臣が学術会議会員候補者の任命を拒否するまでは、歴代の内閣においても、その自律性が尊重されてきたところである。この任命拒否に対しては、当会でも、2020年(令和2年)11月30日付で「任命を拒否された日本学術会議会員候補者の速やかな任命を求める会長声明」を発出している。
このように、学術会議を廃止する立法事実がない。
また、仮に新法人を設置するとしても、本法案の問題点として、次の3点により新法人の独立性が害される懸念がある。
第1に、運営の独立性については、(1)中期的な活動計画や年度計画の作成、予算の作成、組織の管理・運営などについて意見を述べる運営助言委員会(27条、36条)、(2)中期的な活動計画の策定や業務の実績等に関する点検・評価の方法・結果について意見を述べる日本学術会議評価委員会(42条3項、51条)、(3)監査・調査等を行う監事(19条、23条)という各機関の設置により運営の独立性が侵害される危険が高い。
第2に、人事については、(1)学術会議の会員は新法人の会員となるが3年後には再任されないこと(附則11条)によって学術会議との連続性が絶たれる。(2)新法人が発足する際の会員については、会員予定者を選考する候補者選考委員会の委員の任命にあたって、内閣総理大臣が指名する有識者と協議しなければならず(附則6条5項)。(3)その後の会員の選定については選定助言委員会が意見を述べ(本法案26条、31条。以下、条文は本法案のものをいう。)、(4)「会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置」を講じることが求められていること(30条2項、附則7条3項)により、人事の独立性が侵害される危険性が高い。
第3に、財政的な独立性について、学術会議は国の特別の機関とされてきたが、新法人は特殊法人とされるため、政府の財政措置は補助にとどまるとされ(48条)、財政的な独立性が侵害される危険性が高い。このことは、新法人の機能低下の危険や、例えば補助金の増減等によって財政面から運営・人事の独立性が侵害される危険をもたらすものである。
よって、当会は、学術会議を廃止する立法事実がないこと、新法人を設立するとしても、その独立性が損なわれるおそれが大きいことから、本法案に反対する。