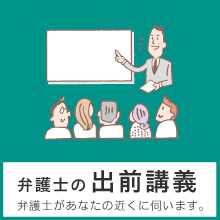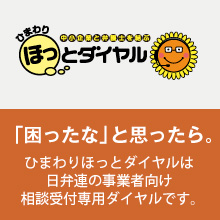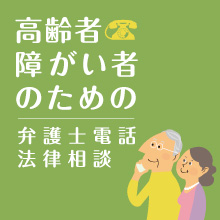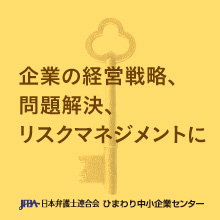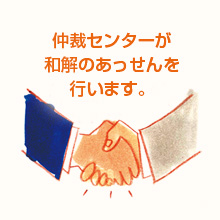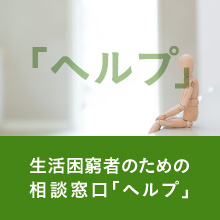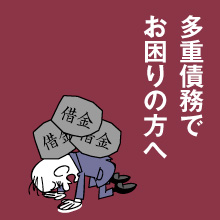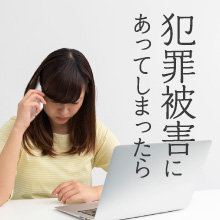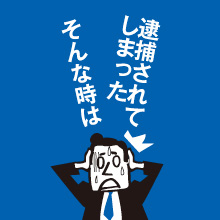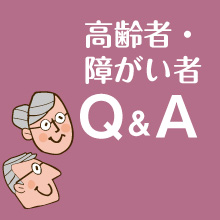会長声明・意見
地方消費者行政に対する財政支援を求める会長声明
2025年(令和7年)8月7日
山口県弁護士会 会長 浜 崎 大 輔
山口県弁護士会 会長 浜 崎 大 輔
1 国は、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の交付期限を延長し、少なくとも同交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置すべきこと
2 2026年度移行を目指して進められているPIO-NET刷新及び消費生活相談のデジタル化において、システム構築・運営のための経費を、全額国が費用負担すべきこと
第2 意見の理由
1 消費者被害の現状、高齢者の被害の増大等
「令和7年版消費者白書(以下「白書」という。)」によれば、2024年の全国の消費生活相談件数は約90.0万件で前年の91.4万件より減少したものの、前々年の87.6万件に比べると増加しており、高止まりが続いている。年齢層別では65歳以上の高齢者が契約当事者全体の33.1%を占めている(白書35頁)。
また相談情報に現れない消費者被害の実態・規模を推計する消費者被害・トラブル額の推計において、2024年は、件数約1940万件、被害額(既支払額(信用供与を含む。))は約9.0兆円(前年約7.9兆円)と報告されている(白書57~58頁)。
山口県においても、「令和5年度の消費生活相談の状況の概要」によれば、同年度に山口県内の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談総件数は2281件であり、前年度(1812件)比125.9%となっている。
このように消費者被害は後を絶たず、依然として深刻な状況である。これらの消費者被害を救済し、被害を未然に防止するためには、相談体制の確保をはじめ地方消費者行政の継続・強化が非常に重要である。
2 地方消費者行政の現状と問題点
2009年の消費者庁・消費者委員会創設以降、消費者行政推進基本計画に基づき、地方公共団体の消費者行政の充実強化に向けて、地方消費者行政活性化交付金(2009年度~2011年度)、地方消費者行政推進交付金(2012年度~2017年度、以下「推進交付金」という。)、現行の地方消費者行政強化交付金(2018年度~、以下「強化交付金」という。)と、国の財政支援策が継続されてきた。
「令和6年度地方消費者行政の現況調査(以下「令和6年度現況調査」という。)」によれば、2024年度の地方消費者行政の予算額は207.8億円であり、このうち強化交付金が約29.6億円(14.2%)、自主財源が約178.2億円(85.8%)である。2018年度以降、地方公共団体の自主財源が少しずつ増加しているものの、特に小規模自治体の多くは交付金に依存しており、自主財源がゼロの小規模自治体もまだ一定程度存在している。
さらに、近年、消費生活相談員の高齢化と新規・若手の相談員の成り手が少ないことによる担い手不足の深刻化が進んでいる。消費生活相談員は、消費者被害に遭った消費者の相談に対応し、事業者との交渉を行うなど、消費者被害の救済において重要な役割を担っている。
この点、2025年3月18日に政府は第5期消費者基本計画を閣議決定し、その中で地方消費者行政について、「消費生活相談の担い手確保が深刻な課題となっている」との認識を示した上で、強化交付金について「地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずる」との方針を掲げている。
3 地方消費者行政推進事業に対する交付金の交付期限到来による影響と国の財政支援継続の必要性(意見の趣旨1について)
推進交付金と現行の強化交付金のうち地方消費者行政推進事業に対する交付金は、消費生活相談員の人件費にも充てることができるだけでなく、様々な消費者行政事業に活用できるものであり、長い間地方の相談体制を下支えしてきた。しかし、2025年度末をもって多くの地方公共団体で同交付金の活用期限が終了し、2027年度には全ての地方公共団体で終了する。
地方公共団体の自主財源は少しずつ増加しているものの十分な程度には達しておらず、交付金の終了によって、相談窓口の維持が困難になり、また交付金で実施してきた啓発・消費者教育等の実施が困難となるなど、地方消費者行政が後退・縮小することが予想される。
消費者庁は、現在、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)を刷新し、消費者向けウェブサイトや相談支援システム、相談分析、情報提供システム等のシステム基盤の整備を行うというデジタル化計画を進めているが、この新システムの目的を達成するためには、自治体における相談業務が安定的に実施され、相談内容のPIO-NETへの入力業務が適時・適切に行われることが必要であり、それを行い得るような自治体の人的・物的体制の確保が必須である。地方の体制整備なくして、国のデジタル化構想の目的を達成することはできない。
以上から、交付金の交付期限を延長すべきであり、少なくとも、同交付金と同様消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置すべきである。
4 消費生活相談のデジタル化及びPIO-NET刷新における国の費用負担の必要性(意見の趣旨2について)
消費生活相談のデジタル化とPIO-NET刷新における地方公共団体の費用負担についても問題になっている。
両方の新システムの導入に必要な端末(パソコン)の設備費用は強化交付金の対象とならず、地方公共団体が負担するとされており、システム利用に係る経常的経費(通信費や保守費等)も地方公共団体負担となる。PIO-NETについては、これまで専用の端末が国民生活センターから必要台数貸与され、その端末を維持するための通信費・消耗品・保守費用も含めて国が負担していたのであるが、専用端末を廃止してパソコン(クラウド)に一本化し、パソコン設備費用は地方公共団体が全額負担するよう求めているということである。
PIO-NETに登録される情報は、相談現場における助言・あっせんのための情報としての役割以外に、法執行の端緒や立法政策の根拠ともなるものであり、できるだけ広く・多くの自治体がPIO-NETに接続することが、国にとっても望ましいはずである。新システム構築の際の経費負担により入力事務が円滑に行えなくなることがないよう全額国が費用負担すべきである。
以上