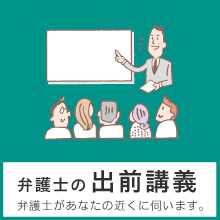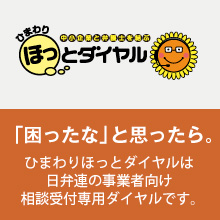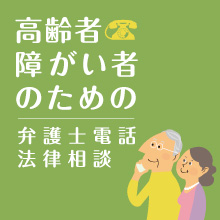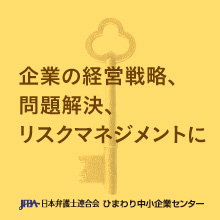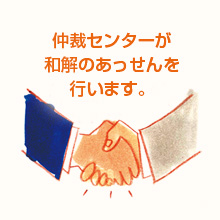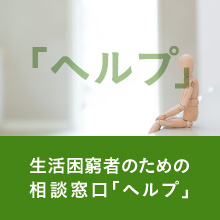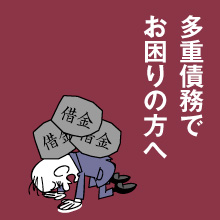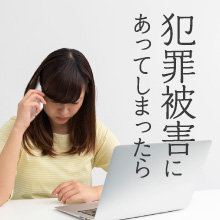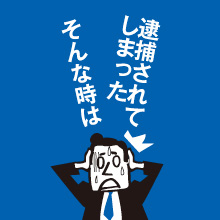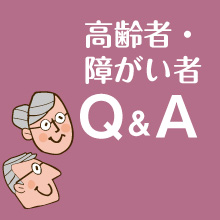会長声明・意見
死刑執行に抗議するとともに、最高刑のあり方についての国民的議論が尽くされるまでの間、すべての死刑執行を停止することを求める会長声明
2025年(令和7年)6月30日
山口県弁護士会
会長 浜 崎 大 輔
山口県弁護士会
会長 浜 崎 大 輔
死刑は、国家が公権力の行使として人命を奪う究極的な刑罰であり、罪を犯した人の更生と社会復帰の可能性を完全に奪い去るものであるから、漫然と継続することは許されず、その存続の可否について常に真剣な検討が必要である。とりわけ、誤判に基づく場合は取り返しがつかないことも考慮されるべきである。
その誤判を正すべき再審制度(刑事訴訟法第4編)は、証拠開示が制度化されておらず裁判所の裁量に委ねられる点が多く、長らく「開かずの門」と言われ機能しなかった。現在でも、上記の再審制度の構造上の問題は改善されておらず、日弁連では2020年(令和2年)6月に再審法改正実現本部を立ち上げた。このような現在の不十分な再審制度の下でも、わが国では、1980年代に4件の死刑確定事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)、最近では2024年(令和6年)にも死刑確定事件(袴田事件)について再審無罪が確定しており、誤判に基づく死刑判決・執行が行われてきた可能性及びこれからも行われる可能性は払拭できない。近年も、死刑事件以外で再審無罪となった事件も相次いでいる。さらに、犯罪事実のみならず情状事実についての認定・評価の誤りも含めれば、誤判による取り返しのつかない事例はより広範に存在する可能性がある。
こうした、誤判により人命を奪うことの「取り返しのつかなさ」への懸念が要因と推測されるが、現在、140か国以上の国が死刑を廃止又は停止しており、死刑の廃止は国際的な趨勢である。2014年(平成26年)7月、国際人権(自由権)規約委員会は、日本政府に対し、死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告した。また、同年12月の国際連合総会において、「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が採択された。さらに、国内でも、2024年(令和6年)11月13日付「日本の死刑制度について考える懇話会」報告書は、国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体の設置を提言し、具体的結論が出るまでの間に死刑執行を停止する立法や死刑執行を事実上差し控えることを検討すべきとした。にもかかわらず、国は、これらに配慮することなく、今回の死刑を執行した。
日本弁護士連合会は、国に対し、死刑制度のあり方について国民的議論が尽くされるまでの間、すべての死刑の執行を停止することを求めてきた。その後、2016年(平成28年)10月7日に福井県で開催された人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを明言した。
また、中国地方弁護士会連合会は、2019年(令和元年)11月1日「死刑制度の廃止を求める決議」を採択した。
当会も、2016年(平成28年)3月5日、袴田事件を題材にしたシンボジウム「死刑を考える日」を主催し、死刑制度について県民に議論を呼びかけた。また、2018年(平成30年)12月26日には、「最高刑のあり方についての国民的議論が尽くされるまでの間、すべての死刑執行を停止することを求める会長声明」を発出し、国民的議論が尽くされるまでの間、死刑執行を停止することを求めてきた。2023年(令和5年)12月2日には、シンポジウム「死刑を考える日」を主催し、死刑制度について県民に議論を呼びかけた。さらに、2024年(令和6年)9月26日には、「袴田事件の再審無罪判決を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明」を発出し、「誤った死刑判決に基づく死刑の執行を防ぐには、死刑制度を廃止する以外に道はなく、当会は、引き続き死刑制度の廃止を強く求める。」と表明した。
このような中、今回の死刑執行が行われたものであり、国民的議論を尽くした末に死刑制度が廃止という結論に至った場合には、今回の執行により絶たれた命は取り返しがつかない。当会としては、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、改めて、国に対し、死刑に関する情報を広く国民に公開し、最高刑のあり方について国民的議論が尽くされるまでの間、すべての死刑執行を停止するよう求める。
以上